読書が進まない時がある。
昔は一冊の本を読み終えるまで、他の本には手を付けませんでした。
ものすごく当たり前のことを言っているようですが、この読み方にはちょっと問題が。
読んでいる本が自分に合わないと読書がなかなか進まなくって、そのうち読書自体に対するモチベーションが下がってしまうのですね。
ずっと同じ本を読んでいると飽きてしまいますし。そうなると読みたいけど読めない・読みたくない、という悪循環に陥ることも。
複数の本を同時に読み進めてみると…?
そこである時から、本Aの進行がはかばかしくない場合は本Bを読み、そしてまたきりのいいところで本Aに戻る、という読み方をしてみました。
すると不思議なことに本Aも本Bも読み始めがすごく新鮮で、互いの内容がすんなり頭に入ってくるようになりました。
もちろん本Bの方がおもしろくって一気に読んでしまう、ということもあります。そんな時は本C、本Dと他の本にどんどん手を出していけばOK。
結果、本Aを読まなくなってしまう場合もありますが、そんな時は見切りを付けてもいいのではないでしょうか。

読んで「合わない」本は、読むのをやめてもいい
読書を始めても「合わない」ことがある 本を読み始めて、または中盤あたりまで読んで、「ちょっとこの本は合わないな」とか「著者の主張が頭に入ってこない」なんてこと、ありませんか? ひょっとしたら本の内容がトンデモだった!という場合もあるかもしれ...
複数本を同時に読んで相乗効果を狙う。
複数の本を同時進行で読み進めることによって意識が分散してしまうのではなく、常に新鮮な気持ちでいられるという相乗効果があるような気がします。
今読んでいる本、ちょっと読み進めるのがしんどい時は、気分転換に別の本に手を出してみてはいかがでしょうか。
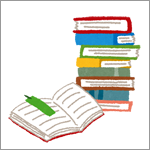


コメント